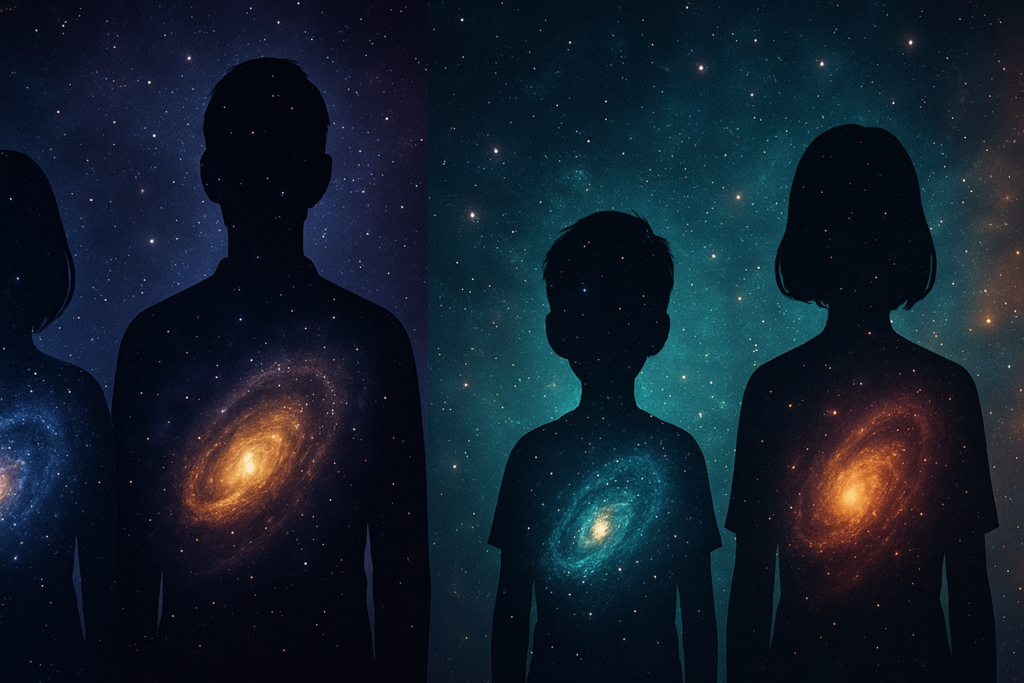
「一人ひと宇宙」から始める唯一無二のコーチング視点
私とあなたは違う。あなたも私と違う。この世に全く同じ人間はいません。そんなことは当たり前すぎて考えもしません、普段は。でも、コーチングでは重要なポイントなんです。
多くの人は、誰かと似たような人生を歩むことを無意識に受け入れ、安心さえ感じるように脳は働いてます。
「◯◯さんが失敗したなら私も無理だろうな」
「45歳になったら老後を心配するのが常識だ」
「タピオカが流行ってるの?私も飲まないと」
「◯◯さんができたんだから私にもできる」
「今年の流行ファッションは何?気になる〜」
グループの中で自分だけが違っていると、安全が脅かされるのでないか、という生存本能。つまはじきされる恐怖。
確かに、大昔はグループからはみ出したら生きていけませんでした。隣の部族に捕まって奴隷になるか、猛獣に食べられて終わりです。
そんな、生まれた瞬間から”安全に長生きしたい”という強い本能を持っている私たちが『誰かと同じにしていれば安全だ』と思ってしまうのは当然のこと。
そして、その真似るべき対象者は自分に近しい人であればあるほど強く影響されます。
例えば、タンザニアのムワンザ市でバスの運転手として働いている67歳のアスマニさんの人生と、あなたの人生は、全く違うと直感的に理解できるはず。真似る対象にはなりません。
でも、家族や両親、昔からの友人ではどうでしょうか?”ちょっとは似てるところあるかも”って思えませんか?親近感が生まれますよね。
ここで完全に確信して欲しいことは、あなたと同じ人間、いや似ている人間など誰一人としていないということ。
男女の性別や住んでいる環境、教育や文化のことを言っているのではなく、あなたの情報宇宙のこと。100人いたら100通りの過去の経験があり、80億人いたら80億通りの人生のパターンがあるんです。皆それぞれ、自分にとって重要なものは全く違う。ある人は、人生で一番重要なものがお金の人、家族の人、ファッションの人、車の人、楽器の人、動物の研究の人、美味しいものを食べる人、重要なことは皆違うんです。
その人生のパターンひとつひとつが唯一無二の宇宙を形成しています。
これをコーチングの用語を使うと「重要性評価関数(じゅうようせい ひょうか かんすう)」と言います。自分にとって重要なものが過去の経験値の中から選ばれて、さらにそれらを重要な順に並び替える関数。
そして、この「重要性評価関数」というフィルターを通して、私たちはそれぞれが違った世界を見ているんです。
例えば、家族で東京タワーの展望台に登って外を眺めたとします。
新宿の高層ビルに目が行くお父さん、地上の歩行者を数える弟、富士山に感動するおばあちゃん。みんな自分にとって重要なものに注目します。それ以外は視界に入っていても重要でないから記憶に残らない。
当然、家に帰って感想を聞けば「東京はビルだらけだな」「人がいっぱいいたよね」「富士山に雪が積もっていて奇麗だったね」と皆バラバラ。
それで良いんです。皆、それぞれ自分の情報宇宙で生きているのだから。
そこに、ひとつの”こうあるべき”を当てはめたら摩擦が生まれ争いと発展し、生きづらい世界になってしまいます。(実は自分自身で”こうあるべき”と摩擦を生んで勝手に生きづらくなっている人は意外と多いのかもしれません・・・)
一人ひと宇宙です。
コーチングで解く頑固マインドと重要性評価関数の正体
「重要性評価関数」がわかると、あることも分かります。
歳をとるほどに様々な経験値が増えます。”人生の先輩”という言葉が意味するように、先に生まれた人から多くの経験値を蓄え、年長者であるほど、尊敬される存在になっていきます(現実は?ですが)
歳をとって頑固になったなぁ、って思うことありませんか?もしくは思い当たる人がいませんか?「私は〇〇な人間だ」と現状の自分をかたくなに守る人。
実は頑固さの原因は「重要性評価関数」が歳とともに複雑に絡み合って強固な網の目が出来上がったからでもあるんです。
頑固なマインドを解きほぐすには「重要性評価関数」を書き換える柔軟性を持つことが重要。
年長者だけではなく、若者でも「私はこういう人間だ」という思いが「重要性評価関数」を強めます。
現状の評価関数を未来の評価関数に書き換えると、別人になります。頑固な老人が、青年のようなマインドに戻ることも可能です。
個性とは?
個性とはその人の「重要性評価関数」によって抽象度の低い物理世界に表現されたひとつの現象とも言えます。先ほどの例でいうと、高層ビルに注目するお父さんと富士山に感動するおばあちゃん、それぞれの個性を生み出しているのが「重要性評価関数」の仕業なんです。
ちなみに、抽象度とは物事の俯瞰の度合いです。
抽象度が高くなるとランダム性が増し、低くなるとランダム性が減り、より具体的なモノになります。
ま、単純に、抽象度が高いのが情報世界で、低いのが物理世界と思っていただいてOK。
そして、物理世界は情報世界の影響をモロに受けているんです。情報が物を生み出しているイメージです。
そして、私たちコーチは抽象度の低い物理的個性には全く興味がありません。どんなファッションが好きで、どんな資格を持っていて、どんな立派な家に住んでいるかは各自にお任せします。コーチが重要視するのは精神的個性。なぜなら人生を変えるということは、その人の精神的個性を変えることだから。
そして、この精神的個性に直結しているのが「重要性評価関数」。直結と言いますか、イコールって言っていいでしょう。
世間では「個性を磨く」というと、ファッションにこだわったり、新しく習い事を始めたり、自分の長所を伸ばしたり、海外で瞑想したりすることを言いますが、コーチングでは「重要性評価関数」を進化させることを「個性を磨く」と捉えています。
もちろん、進化させる目的は現状の外側のゴールを設定・達成するため。
他人と比べることの無意味さ
以上の説明で、他人と自分を比べることが、いかに無意味であるかが分かっていただけると思います。
一人ひとり全く違う「重要性評価関数」で世界を見ているので、比べることに意味がないわけです。
東京タワーの展望台で、高層ビルに関心しているお父さんと、富士山に感動しているおばあちゃんとを比べて、どちらが正解かなんてないんですよね。
ましてや時間軸を含む”人生”という流れの中で他人と違うことは当然。同じ人生を歩む人は全くいないということは、同じ瞬間を生きる人もいないということ。
「わかるけど、どうしても他人と比べてしまうんです」
わかります、その気持ち。なぜなら私たちは他人と比べる癖がついているから。
それは、何かと比べるという相対的な判断基準によって自分の存在(存在価値)を確認することに慣れすぎてしまっているから。身体的な違い、能力の違い、持っている資格の違い、生まれ育った環境の違い、文化の違い、などなど。なんでもかんでも比べる癖がついてしまった。「他者と自分との差が個性である」と。極端に聞こえるかもしれませんが、この”比べる”行為が争いや差別の種になっているのではないかと私は思っています。
もう、(他者と比べた)個性で悩むのはやめましょう。皆それぞれが素晴らしい個性の持ち主であり、可能性の塊であり、一人ひと宇宙の中で「これが私だ」と胸を張っていいんです。
比べるべき相手は、未来の自分です。
未来のぶっ飛んだゴールを達成している自分自身と現在の自分を比べればいいんです。
あとで詳しく解説しますが「重要性評価関数」を書き換えるには現状の外側のゴールが必要です。今の自分では達成できないほど大きなゴールを未来に設定して「私にはゴールを達成する能力がある」と確信(エフィカシー)するこで自分にとって重要なものが変わります。
将来、ぶっ飛んだ理想のゴールを達成したあなたは、現在のあなたと全くの別人になっているはず。そんな理想のあなたと現在のあなたを比べることで発生する認知的不協和こそが行動のモチベーションになるんです。
ちなみにエフィカシーが低いと「自分にはゴール達成は無理かもしれない」という諦めの感情が生じてしまいます。コーチングがなぜゴール設定と高いエフィカシーの維持が主軸であるかも、以上の解説でなんとなく理解していただけたかなと思います。
人生に制限はいらない!コーチングで描く理想の未来
「自分の人生は好きなように使って良い」
これは譲れない真実です。
コーチが興味があるのは、あなたの変革であり、それによってあなたの人生がどれくらい進化・拡大するかの一点です。コーチはあなたの未来の成功(ゴール達成)を確信しいてます。”信じている”のではなく”確信”です。なぜなら成功するから。「重要性評価関数」を書き換え、現状の外側のゴールを設定し、クラクラするくらい高いエフィカシーを持った人が成功しないはずがありません。
あなたは自分の人生を好きなように生きていい。
コーチングでは24時間365日Want to(〜したい)だけをする人生が正解であると伝えます。1ミリもHave to(〜しなければならない)なことをしなくていい。そりゃそうですよね、本心で達成したいゴールであれば、そこに向かう過程はすべてWant toだし、例え壁にぶつかってもゴールに近づく壁ならウェルカム。もしHave toを感じるのであれば、ゴール設定が間違っているか、そもそもゴールがないかのどちらかです。
どんどんWant toをすればいい。
明日、会社を休んでヨーロッパ旅行に行ってもいい。約束をドタキャンして友人と野球観戦に行ってもいい。欲しかった高級車のディーラーと今すぐ会って契約書にサインしてもいいんです。
行動に移す際に「できるか・できないか」ではなく「やりたいか・やりたくないか」で判断する。これが現状の外側のゴールを達成するために重要なマインド。達成方法は脳がクリエイティブに生み出してくれます。元祖コーチングのルー・タイス氏が言う”Invent on the way(達成方法はやりながら発明する)がまさにこれ。
「できるか・できないか」で判断し「できる」ことだけをやっている限り、いつになっても現状の外側には行けません。「やりたいこと」を選択して初めて脳はクリエイティブに働きだします。自分の脳を過小評価せず、無限の可能性が眠っていることを確信しましょう。
自由への切符(やりたいことだけで生きる方法)
「でも、わかっちゃいるけど・・・」
分かります、その気持ち。私もコーチになる以前は、やりたくないけど我慢していました。生活のため、家族のため、常識を守るため。「できること」だけをせっせとこなし、「やりたいこと」を後回しにして生きてきました。Want toだけの人はワガママだ、と。
コーチになった今だから確信していることは、Want toで生きることが正しい生き方だ、ということ。
当たり前ですが、やりたくないことをやっても脳はクリエイティブに働きません。生産性もなければ、継続する力も失われます。(クリエイティブアボイダンス)規則に縛られて、まさに奴隷のように生きるだけ。奴隷とは、やりたくないことを強いられる人のことです。
奴隷から抜け出して、自由な人生を手に入れるにはWant toな生き方だけです。
自由を手に入れる方法は簡単。
自己責任を100%受け入れるだけ。
自己責任を100%受け入れた人から順に自由を手に入れます。
100%自己責任を受け入れれば、今すぐヨーロッパ旅行にも行けるし、フェラーリの契約書にサインもできます。もしそれが本当に心から望むのであれば。自己責任がまだ薄い未成年なら、それくらいの勢いはありますよね。明日、無断で学校を休んで友達と隣町にサイクリングに行ってバカ騒ぎできる。
自分の宇宙で責任を取れるのは自分だけです。
自己責任は恐ろしいものでも、避けるべきものでもありません。自由への切符です。社会人である私たちは本心では理解しているはず。
会社では上司からの命令は絶対です。社長の言葉は神の言葉と同じです。歯向かうことはできません。なぜなら、あなたの業務で起こった失敗の責任を取るのは上司であり社長だからです。もちろん、あなたは叱られ、注意されるでしょうが、実質的な責任を取るのは上司であり社長です。
あなたが自己責任を”取りたくても取れない”のが会社。
じゃ、会社で自由に業務をさせてもらう方法はないのか?あります。明日、社長にこう言ってみてください。「今回のプロジェクトは100%自己責任でやらせてください」と。社長が受け入れるかどうかは分かりませんが、自由にするために必要な最低条件ですよね。
「自由にさせてください」=「自己責任を取らせてください」
人生においても全く同じです。自己責任を受け入れた人から順に自由を手に入れます。
コーチングで叶える社会性のある自由な人生設計
自由は我がままとは違います。
”我がまま”を辞書で引くと、「他人や周囲などの都合や事情を考えずに、自分勝手に振る舞ったり発言したりすること」とあります。
つまり、他人と自分を比べ、他人をさげすんだ思考や行動をわがままと言います。自己中心的、利己的、自分本位な考え方です。
自由とは我がままに振る舞うのとは違います。だからゴール設定の三原則に社会性が含まれるのです。
(ゴール設定の三原則:1現状の外側であること、2本心から達成したいこと、3社会性があること)
社会性が高く(大きく)なると抽象度も自然と高くなります。抽象度とは物事を見る際の俯瞰レベル。抽象度が低いと利己的な思考になり、抽象度が高くなると利他的な思考が生まれます。
大乗仏教に「煩悩即菩提(ぼんのうそくぼだい)」という言葉があります。
煩悩を否定せず、むしろ”悟るためには煩悩も肯定する”という意味が含まれています。自分が悟ることを第一義とする小乗仏教とは違い、より多くの人を悟りに導きましょうという教え。自分だけが幸福よりも、家族、友人、隣人、国民、世界の人々全員が幸福になることが善であるという教えです。
コーチングでゴールに社会性を求めるのもこれと同じで、より多くの人に利益を共有できるゴールであるべきなのです。抽象度を上げると必ず社会性も大きくなります。
近しい友達とだけ仲良くなりたいという抽象度の低いゴールではなく、世界中が仲良くなり、戦争や差別がなくなる世界を本気で実現しようと日々活動されているのが苫米地博士であり、コーチです。
コーチはぶっ飛んだゴールの達成を確信できる数少ない稀な職業です。言い方を変えると、小さな欲ではなく大きな欲を本気で求めている。世界を平和にしたい!なんて、どれほど大きな煩悩でしょう。
それでいいんです。世界平和に本気になって何が悪いのか、ということです。
社会性の高い(大きい)ゴールはたくさんの人を巻き込みます。たくさんの人を巻き込めば、結果的には大きな利益が自分に返ってくるわけですが、そこは期待しない。期待した瞬間に抽象度は一気に下がってしまいます。いうまでもなく、自分だけ満たされればいいというゴールは抽象度が低すぎてダメ。なにがダメかというと、行動力が生まれません。
世間でいわれる理想の人生とは、自分だけが成功することを目的にしたものばかり。理想の生活、理想の職業、理想の収入、理想の人間関係、どれもこれも自分のため。よくて家族を含む身近な人だけで共有できる幸せです。
あなたの理想はそんなものじゃないですよね。
世間の理想から大きく外れたところに自分の理想があるはずです。さらには、その自分の理想ですら大きくはみ出すくらいぶっ飛んだゴールを設定して「私にはゴールを達成できる能力が備わっている」と確信する。この作業がコーチングのファーストステップであり、最も重要なテーマなのです。
最後にあなたへの注意喚起も含めて、興味深い話をしますね。
コーチングのセッションを受けると、頭痛、吐き気、動悸(どうき)、ふらつきが起こることがよくあります。私も初めてコーチングのセッションを受けた帰り道、風邪でもないのに頭痛とめまい、それと軽い記憶障害が起こり、帰り道を間違えた経験があります。頭痛は翌日も。もちろん病気ではないので元に戻ります。
これは、セッションによって現状の自我が思いっきり揺さぶられたから。これまでの古い自我が壊れ、新しい自我に生まれ変わる時に精神的、身体的な抵抗が起こります。「変化しちゃだめ、今のままでいいよ」「新しい自我に生まれ変わるのは危険だよ」と古い自我がもがき出します。これが内なるドリームキラー。ドリームキラーがあなたを現状維持に止めようと懸命になります。絶対に耳を貸さないでください。完全スルーしてください。
また、苫米地博士のセッションを受けると、その帰りに車で事故を起こす人が続出することはコーチの間では有名な話。博士も「車では来ないでね」とクライアントさんに注意されるそうです。
それくらい、私たちの無意識は現状に居心地の良さを感じて、現状を壊すことに抵抗するということです。世間の理想に慣れ親しんだ私たちは、口では変わりたいと言っても無意識は変わりたくないと抵抗するのです。
どうですか?あなたの無意識はどんな反応をしていますか?
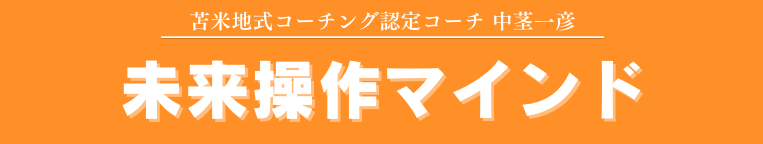



コメント